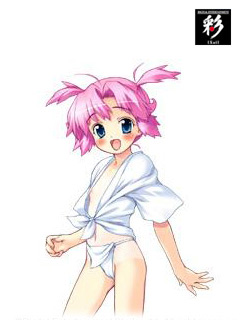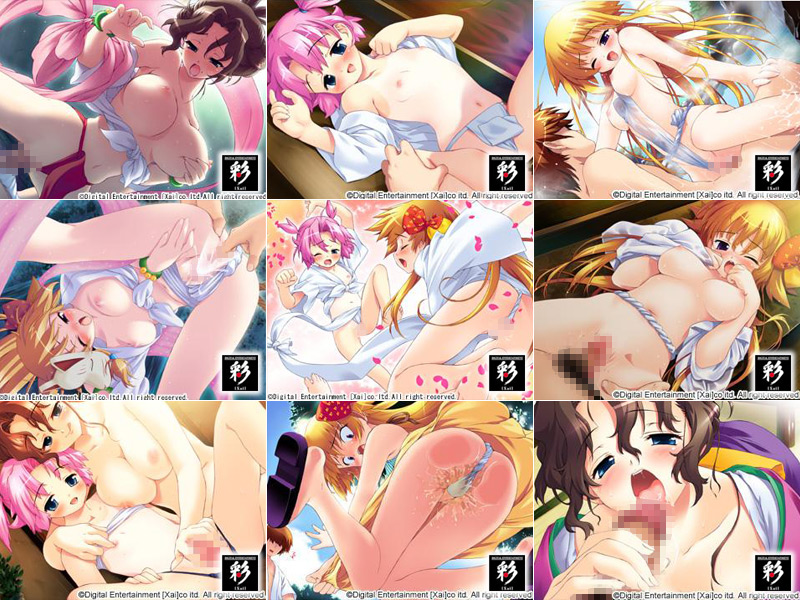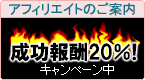都会の喧騒を離れ、無人の終着駅の向こう。セミの大合唱と土の匂い。真夏の日差しは稲穂を輝かせている。
四方を山に囲まれて、ひっそりと存在し続けるその村には、今も昔も変わらぬ祭りの姿が受け継がれていた。
文化人類学専攻の学生・木崎英仁の目的はその祭りにあった。
親戚を頼り、夏休みを利用してこの村のフィールドワークを予定している。
そんな英仁を迎えたのは、褌姿の女のコと9日間のお祭りだった。
【褌紹介】
・褌の利点
玉の座り具合がいい。通気性が非常にいい。(袋が二重の場合は蒸れる) 下腹が引き締まるので胃の働きにいい…らしい。尻の布地が張り付かなくていい。襦袢など、上に着る布地の心地良さが尻で味わえる。(新鮮らしい。)靴を脱がなくても外せるので衛生的。(主に軍人曰く。)
《越中褌》
前垂れのある、現在最もポピュラーな褌。六尺褌を短くし、端に結び紐を取り付けたもの。締めこまない“ゆるフン”でお手軽だが、うっかり袋(股間部分)が緩み、お宝が横から覗いてしまうことも。手軽で、布地が少なく蒸れないので、夏場に最適。お医者様も進めるくらい健康にいいらしい。縁がなかった子宝に恵まれた。肩こりが治った等。
《六尺褌》
「褌を締め直す」とはこのこと。一枚の布をしっかり締めこむために、下腹が引き締まり、ピリッとした緊張感と高揚感を生み出す。前垂れで、袋(股間部分)を二重にまわした為に蒸れるので、夏場にはインキンに悩まされた人も。
《割褌》
六尺褌の一種で、布地の中頃から2股に分かれているもの。分かれた布地を横回しにする。後にこれがより短く、布を節約した越中褌になったようだ。
《九尺褌》
漁師や祭りなどに使われる六尺以上の褌。股間を締めたあと、横回しを2重にしたり、腹巻き、「鳥串踊り」に見られる様に肩にまわしたりした。
《もっこ褌》
褌の両端に紐を通す穴がついており横で結ぶ。ビキニに近い。いわゆる”漢”の部分を意識させる前垂れのないこの褌は、歌舞伎の女形などに愛用されたそうである。
《黒猫褌》
主に海水着として用いる黒い褌。水褌ともいう。学生はこれに名札を縫い付けて使用したようだ。水泳パンツが台頭してくると、サポーターとしても利用された。
《風呂褌》
風呂に入る時用の褌。熱い湯につかる場合、デリケートな部分を保護するために締められていた。劇中では割褌を使っている。